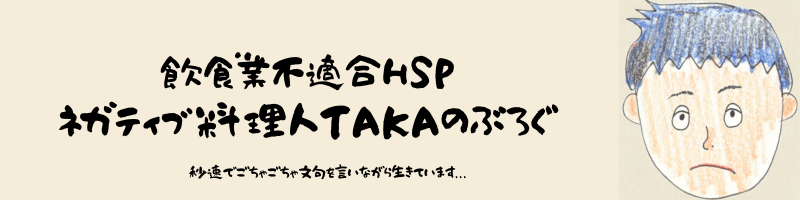とろみをつけるとは、スープや汁もの、煮ものなどの料理に軽く粘りをつけることです。
とろみをつけることによって料理が冷めにくくなったり、のどごしががよくなるなどの効果があります。
家庭料理の他にも、介護職にとろみをつけた料理を作ることが多いようです。
とろみ材料の種類やおすすめの料理レシピを紹介します。
とろみ材料の種類
とろみをつける材料は色々ありますが、それぞれの料理に合ったものを使うことで、より料理が引き立ちます。
片栗粉
片栗粉はカタクリのでんぷんのことですが、馬鈴薯のでんぷんを片栗粉と呼んでいます。
中華料理のあんかけや日本料理のとろみづけに使われます。
片栗粉でとろみをつける際のポイントは、一度水に溶いてから使うことです。

水溶き片栗粉はいっきに加えず、回し入れるようにして全体に行き渡るように入れ、手早く混ぜます。
簡単かきたま汁のつくり方(2人分)
材料:卵1個、だし汁360cc、醤油小さじ1杯、塩少々、片栗粉 小さじ1杯、水小さじ2杯、三つ葉 少々。
①卵1個は溶きほぐしておき、片栗粉は水で溶いておく。だし汁を熱して、醤油小さじ1杯と塩少々で味を整えておく。
③中火にして水溶き片栗粉を全体に回し入れ、煮たたせる。
④溶き卵を回し入れ、器に盛り、三つ葉をあしらいます。
小麦粉
小麦粉も片栗粉と同じようにとろみをつける料理に使いますが、小麦粉は小麦が原料です。
小麦粉はとろっとしてほしいカレーやシチューなどを作るのに適しています。
簡単カレーうどんのつくり方(2人分)
材料:うどん2玉、めんつゆ(3倍濃縮)50CC、カレールー2片、豚バラ100g玉ねぎ2分の1個、細ネギ1本、小麦粉小さじ1杯。
①うどんはゆでておきます。
②麵つゆと水を入れ、玉ねぎを薄くスライスしたものと豚肉を入れ、アクを取りながら煮ます。
③具材が煮えたらカレールーを入れて混ぜながら煮ます。カレーがなじんだら小麦粉を水で溶いて加え、とろみをつけます。
④器にゆでたうどんを入れ、カレーをかけ、ネギの小口切りをトッピングします。
葛粉
葛粉は、葛(クズ)の根から抽出したデンプンを精製したもので、水と混ぜてから加熱すると透明になり、冷やすと固まります。
くずきりやくずもちなどの和菓子に使われます。
簡単葛湯のつくり方(1杯分)
材料は、葛粉10g、熱湯100㏄砂糖適量です。
つくり方は、温めた器に約10g葛粉を入れ、ぬるま湯でよく溶きます
次に沸騰したお湯を注ぎ手早く混ぜ、好みで砂糖を加えます。
コーンスターチ
コーンスターチは、トウモロコシから作られているデンプン粉です。
白い粉末で、片栗粉と同じ性質を持ち、水で溶いて加熱すると、とろみをつけることが出来ます

コーンスターチでつけたとろみは時間がたって冷えても持続するので、カスタードクリームの材料やゼリーやプリンの凝固剤としても使われます。
コーンスターチはとろみをつける以外にも、焼き菓子に使うと、サクサクとした軽い食感に仕上げることもできます。
カマンベールチーズソースのつくり方
材料料:カマンベールチーズ100g、生クリーム200ml、塩コショウ、コンソメスープのもと1個、コーンスターチ大さじ2分の1杯、水大さじ1杯
つくり方は、フライパンに生クリームを入れ、カマンベールチーズと固形スープの素を加え、弱火でこげないように煮ます。
とろみが出てきたら塩コショウで味を調え、コンスターチと水でとろみをつけます。パンにつけたり、温野菜サラダなどにつけて食べます。
ゼラチン
ゼラチンは、動物の骨や皮に多く含まれるコラーゲンというたんぱく質から作られたものです。
ゼリーなどのおやつに使用します。
板ゼラチンはたっぷりの冷水に約20分ほど漬けておきます。
粉ゼラチンは50~60℃のお湯で溶いて使用します。
寒天
寒天(かんてん)は、テングサ(天草)、オゴノリなどの紅藻類の粘液質を凍結・乾燥したもので、棒寒天、糸寒天、粉寒天があります。
棒寒天と糸寒天は、天草が原料で、粉寒天はオゴノリが原料です。
同じ天草を原料としたものにところてんがありますが、寒天は乾燥させたもので、ところてんは天草を煮て固めたものです。
寒天は磯の香りがしないので、料理やお菓子に使うことが多く、磯の香りがするところてんはそのまま食べることが多いようです。
*他にもコンブ、オクラ、モロヘイヤ、ナメコ、サツマイモ、ジャガイモ、ナガイモなどの食材でもとろみを付けることができます。
介護食におすすめのとろみ料理
高齢になると、食べ物をうまく飲み込めない嚥下障害になりやすい傾向にありますが、料理に軽くとろみをつけることで、飲み込みやすくなります。
しかし、とろみをつけると逆に誤嚥のリスクが高まる場合もあるので、個人の様子を見ながら取り入れていきましょう
誤嚥性肺炎を予防するために
誤嚥とは、嚥下障害により、食べ物や飲み物が胃ではなく気管に入ってしまうことです。
気管に入った食べ物や飲み物と一緒に細菌が肺に入ってしまうことがあり、中で炎症を起こし、誤嚥性肺炎につながる危険性があります
介護食用のとろみ剤について
現在では介護食用として市販のとろみ剤があります。

とろみ剤は食物繊維でできており、無味無臭なので、食事の味を変えることがありません。
市販のとろみ剤は、使い方を守れば形状が安定します。
片栗粉やゼラチンと違い、唾液や室温でとろみが消えることもありません。
とろみ食が初めてという方でも安心して使用できるところが最大のメリットで、介護食に適しています。
とろみの濃度について
ポタージュ状の薄いとろみは、ストローでも簡単に吸えるので、介護食として適しています。
とんかつソース状の中間のとろみは、口の中でゆっくりと広がります。
濃いとろみはスプーンを使って食べる形になり、介護食とは言え普通食とほとんど変わりません。
とろみ食としてのおかゆについて
全粥はお米に対して水を5倍にします。お米100gに対して水が500㏄になります。
七分粥はお米1に対し水7倍にします。お米70gに対して水500ccになります。
五分粥はお米1に対し水10倍にします。お米50gに対して水500ccになります。
三分粥はお米1に対し水20倍米にします。25gにに対して水500ccになります。
食材のとろみを利用して料理を作る
ポタージュにはカボチャを使ってとろみを出したり、味噌汁にはとろろ昆布でとろみをつけるなど工夫することで、とろみ剤を使わなくても、介護食が作れます。
オクラなどもさっと湯通ししてミキサーにかけると、のど越しがよくなります。
また、納豆や長芋なども一緒にミキサーにかけ、柔らかめのご飯や刻みうどんにかけると、栄養価の高いネバネバ丼やネバネバうどんが出来上がります。
調味料でとろみを出す
砂糖は粘度を上昇させ、しょうゆや酢だと粘度は低下します。
油はでんぷんを加えることで乳化されるため、粘度が上昇します。
片栗粉や小麦粉などを使ってとろみを出す場合は、料理が熱すぎると口の中が炎症を起こすことがあるので気をつけましょう。
まとめ
とろみをつけたあんかけ風の料理は冬の料理と思いがちですが、クーラーで冷えたお腹をじんわりと温めてくれます。
また、ゼラチンや寒天を使ったデザートはアイスクリームやかき氷ほど、胃を刺激せず
夏バテを防いでくれます。
今まで、普段の食事に、とろみのあるおかずを作らなかった方も、日々のお惣菜づくりに片栗粉や小麦粉などを使って簡単な料理を作れるようにしておくと、レパートリーが広がります。